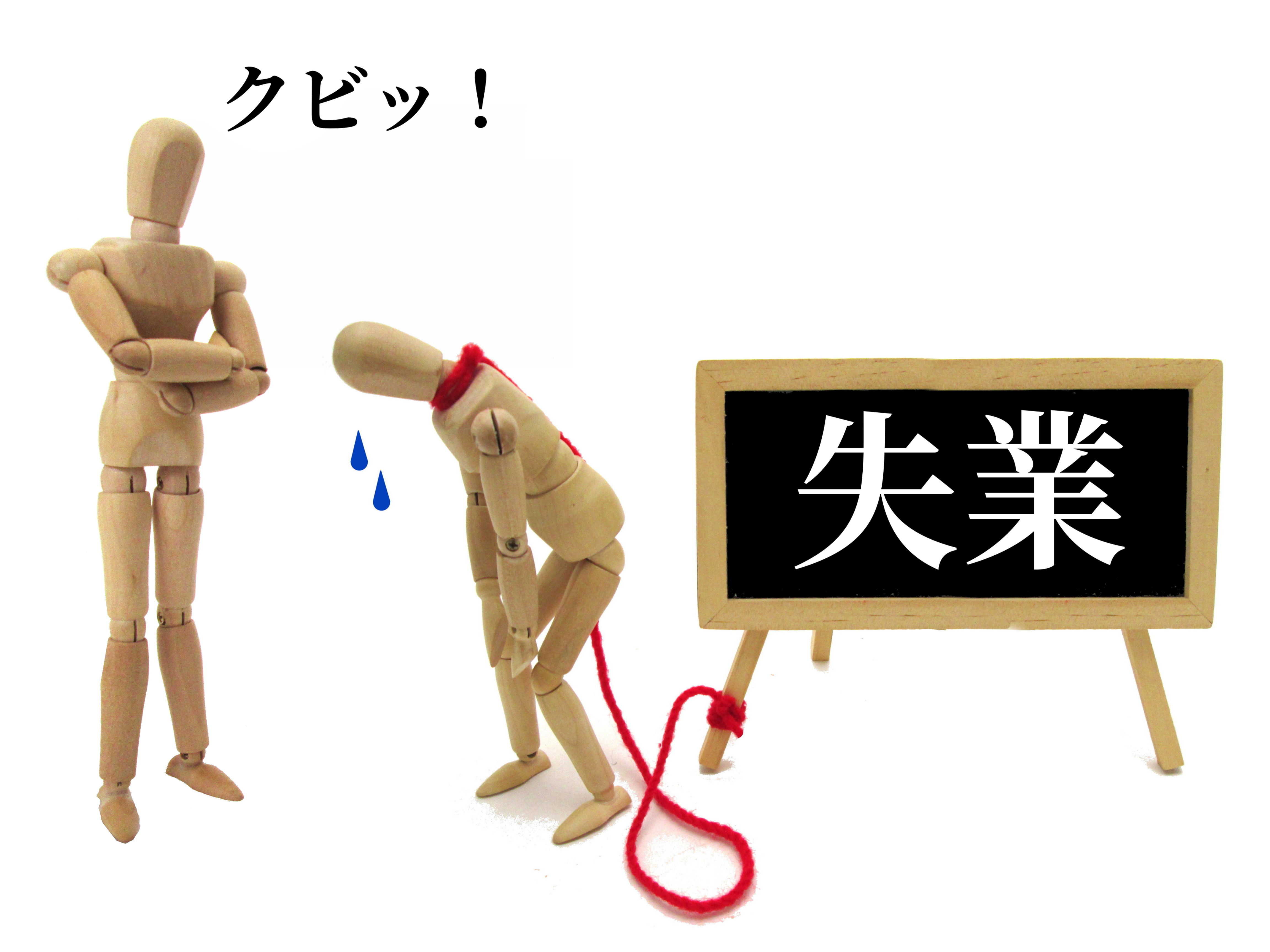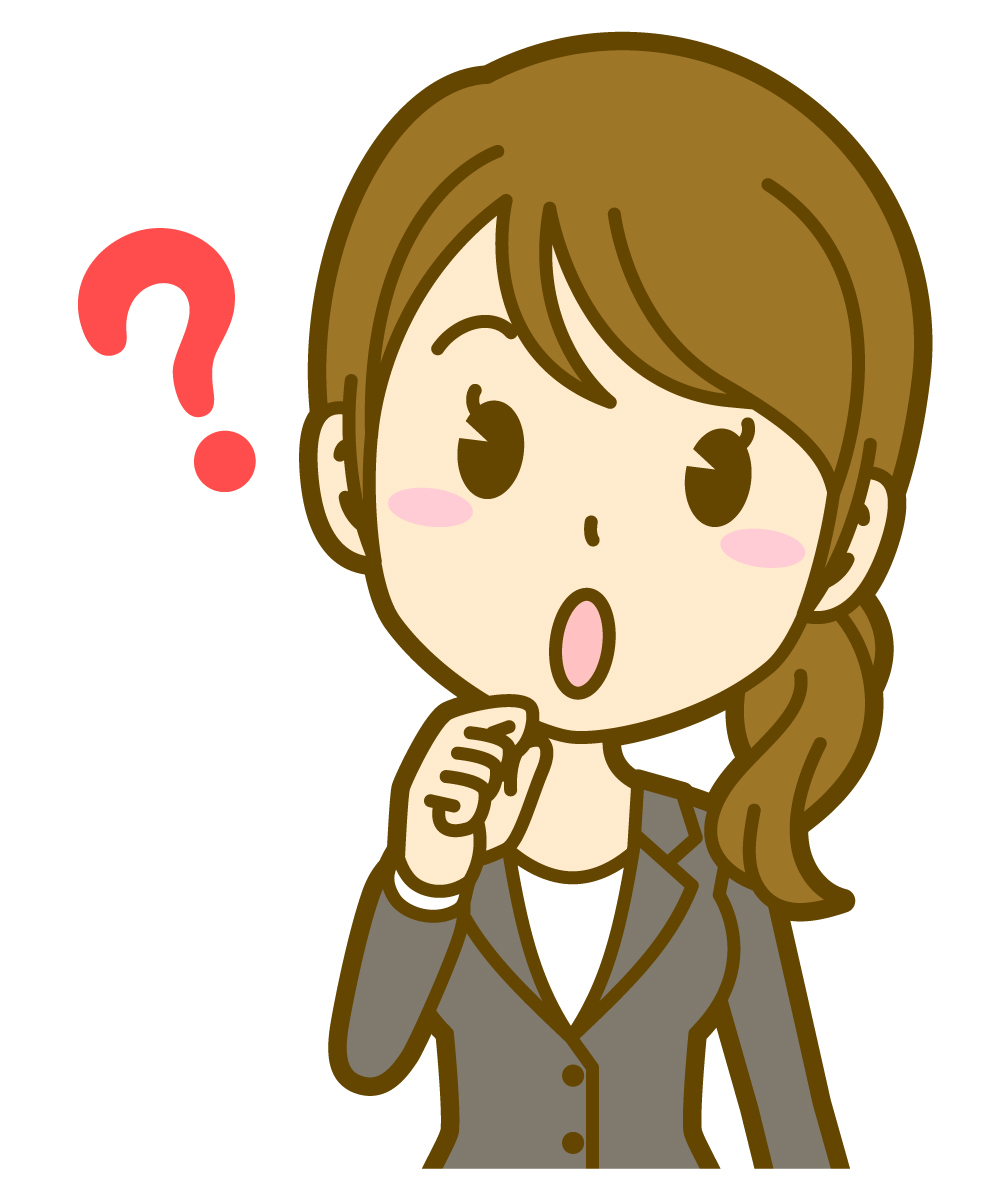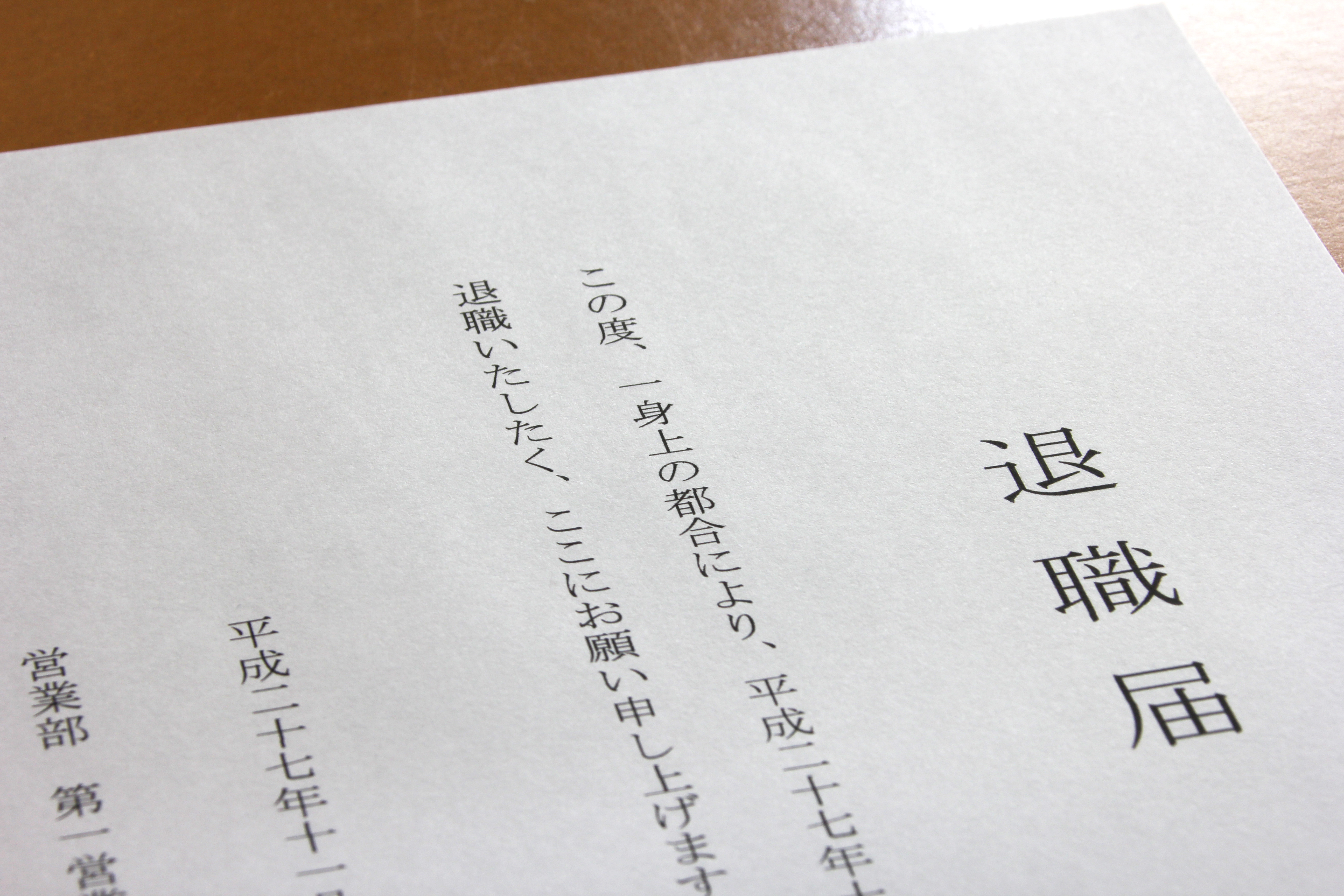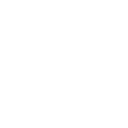パワハラを巡る内紛を理由とする懲戒解雇
先日,ブログで紹介しましたが,パワハラを防止するための法律案
が閣議決定され,今後,会社は,パワハラを防止するための
措置を講じる必要がでてきます。
https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/201903257760.html
そのため,会社は,労働者からパワハラの相談を受けて,
調査をした結果,パワハラの事実があると判断すれば,
パワハラをした労働者に対して懲戒処分を
科すことを検討することになります。
しかし,この懲戒処分を適切に科さないと,
懲戒処分を受けた労働者から,懲戒処分の無効を主張されて,
裁判に発展していくこともあります。
本日は,パワハラを巡る内紛を理由になされた,
幼稚園の園長に対する懲戒解雇の効力が争われた,
学校法人名古屋カトリック学園事件を紹介します
(名古屋地裁岡崎支部平成30年3月13日判決・
労働判例1191号64頁)。
原告の園長は,ある職員に対して,送迎バスの添乗時に
保護者や園児に不遜な態度をとるなど,
振る舞いや勤務態度を問題視していました。

他方,ある職員は,原告の園長に対して,
幼稚園の運営が強引で独善的であるとか,
職員に対する原告の言葉の暴力がひどすぎると感じ,
原告に対して,批判的・反抗的な態度を示して,
原告と対立していました。
そのような対立状況の中,ある職員は,
幼稚園の経営者に対して,原告の園長から,
「給料泥棒」などの暴言を浴びせられたので,
園長を交代させてほしいという嘆願書を提出しました。
幼稚園の経営者は,原告を呼び出し,
嘆願書について説明を求め,原告に対して,
事態を収拾するように説得し,原告は,
これに応じて,職員に謝罪しました。
しかし,その後も原告の振る舞いが変わらないとして,
再度,園長交代の嘆願書が提出され,幼稚園の経営者は,
原告が嘆願書に記載された言動をしたと判断して,
原告を懲戒解雇しました。

懲戒解雇の理由は,
①幼稚園又は他の職員の名誉又は信用を傷つけること,
②いたずらに感情に走り,他の者を誹謗したり,排斥すること,
③職務の遂行が越権専断的となること,
に該当するということです。
裁判所は,①と②の懲戒理由について,被告は,
職員の嘆願書を根拠に,嘆願書記載の原告の言動があった
と判断しましたが,それを裏付ける客観的な証拠がないことから,
たやすく嘆願書記載の原告の言動があったとは認定できないとしました。
また,③の懲戒理由について,原告が職員に謝罪をして
事態の収拾が図られていたとして,
情状が極めて重いとはいえないとしました。
その結果,原告には,懲戒解雇に該当する行為をしたとはいえず,
懲戒解雇は無効となりました。
そして,原告の雇用期間があと2年間残っていたことから,
2年分の未払賃金の請求が認められました。
他方,原告は,懲戒解雇による精神的苦痛を被ったとして,
慰謝料の損害賠償請求をしていましたが,
裁判所は,解雇が無効であると判断されて,
未払賃金の支払いを受けることができるようになるので,
なお償われない精神的苦痛が残るとは認められないとして,
慰謝料請求は認められませんでした。
解雇事件において,未払賃金請求と一緒に
慰謝料の損害賠償請求をしても,
なかなか認められないのが現状です。
本件事件では,被告が,原告の園長のパワハラの有無を,
丁寧に調査せずに,一方当事者の主張のみを理由に
懲戒解雇をしてしまったがゆえに,裁判になって,
懲戒該当理由がなかったと判断されました。
今後,パワハラを巡る労使紛争が増加していくことが予想されますが,
会社は,パワハラの事実があったかなかったかについては,
入念に調査した上で,懲戒処分をくだしていく必要があります。

特に,懲戒解雇をする場合には,より慎重な調査が求められます。
本日もお読みいただきありがとうございます。