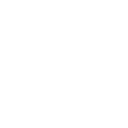労働審判における口外禁止条項が違法になる場合
1 口外禁止条項とは
不当解雇や未払残業代請求といった労働事件の裁判で和解するときや、
労働審判手続で調停をするときに、会社側から、和解条項や調停条項に、
口外禁止条項をいれることを求められることがよくあります。
口外禁止条項とは、「申立人と相手方は、本件に関し、
正当な理由のない限り、第三者に対して口外しないことを約束する」
という内容のものであり、要するに、
事件のことをしゃべってはいけないというものです。

なぜ、会社が、このような口外禁止条項を求めるのかといいますと、
会社が労働者との間で紛争になり、会社が労働者に対して、
いくらかの金銭を支払ったことが明らかになれば、
他の労働者も、会社に対して、同じような請求してくるかもしれず、
会社は、それを防ぎたいからなのです。
特に、未払残業代請求事件の場合、
請求をしている労働者だけが、
残業をしていることは稀で、
他の多くの労働者も同じように残業していることがほとんどなので、
他の労働者からも未払残業代請求をされたくなので、
会社は、口外禁止条項をいれたがります。
通常の労働事件ですと、その労働事件だけを解決するだけでよく、
他の労働者のことをあまり考えませんし、仮に、
口外禁止条項をいれたとしても、
当事者の労働者が口外禁止条項に違反して、
情報を漏らしたことを立証することは困難なので、
ある種の紳士規定としての意味しかないので、私も、
これまでは口外禁止条項に、それほど抵抗していませんでした。
2 労働審判の口外禁止条項を違法と判断した長崎地裁令和2年12月1日判決
この口外禁止条項について、重要な判決がありました。
長崎地裁令和2年12月1日判決です。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG043XK0U0A201C2000000
この事件では、もともと労働者に有利な230万円の解決金を
会社に支払わせる労働審判が宣告されたのですが、
この労働審判に、口外禁止条項がいれられました。
労働審判手続において、相手方の会社から、
口外禁止条項をいれるように求められましたが、
申立人の労働者は、支えてくれた同僚に報告できなくなることを
避けるために、泣きながら、
「終わったということは伝えたい。
同僚が励ましてくれて、それが精神的な支えになってきた。
それを何もなしでは済まされないと思っている」
と裁判所に伝えたようです。
それでも、労働審判で口外禁止条項がはいってしまったので、
申立人の労働者が国に対して、
慰謝料を請求する国家賠償請求訴訟を提起したのです。
長崎地裁は、労働審判について、
事案の解決のために相当なものでなければならないという
相当性の要件が必要であると判断しました。
そして、相当性の要件を満たすためには、
労働審判の申立ての対象である労働関係に係る
権利関係と合理的関連性があるか、
手続きの経緯において、当事者にとって、
受容可能性及び予測可能性があるか
といった観点から検討することとなりました。
本件事件において、第三者に口外されることで、
不正確な情報が伝わることにより、
無用な紛争を未然に防ぐために、
合理的関連性はあり、本件口外禁止条項は、
当事者にとって、不意打ちではなく、
予測可能性もあると判断されました。
もっとも、当事者に過大な負担となるなど、
消極的な合意されも期待できないような場合には、
当事者が明確に拒絶した調停案と同趣旨の労働審判は、
受容可能性はないというべきであるから、
相当性の要件を欠くことになると判断されました。

そして、申立人の労働者は、将来にわたって、
本件口外禁止条項に基づく義務を負い続けることになり、
その心情と併せれば、過大な負担を強いることになるので、
受容可能性はなく、違法と判断されました。
労働審判における口外禁止条項が違法と判断されたのは、
初めてであり、画期的な判決です。
安易に、口外禁止条項を設けると、
会社の違法や不正を隠蔽することにつながってしまうので、
しっかりと抵抗することが大切ですね。
この判決を受けて、口外禁止条項には安易に妥協せずに、
しっかりと交渉していこうと考えました。
本日もお読みいただきありがとうございます。